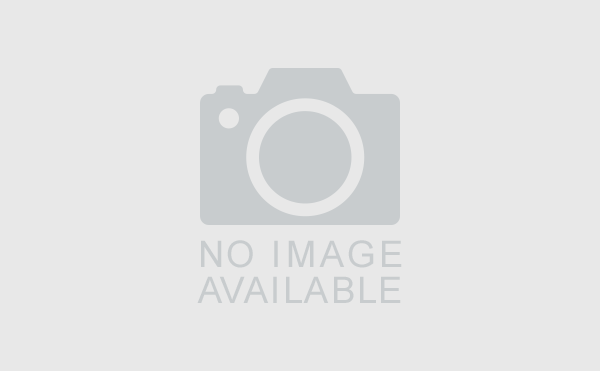ヘッドフォンまつりのQ&A、反省点など
ご来場いただいた方、ありがとうございました。試作ハイエンドDACの反応も8割くらいは好印象のようで今後に期待が持てる展開となったと思っています。製品はこの方向性のまま進めます。
ただ当日はマラソン試聴会もありましたし他にも魅力的な出展があったのか、去年よりも人の数自体が少なかったように思います。それでも常に誰かに試聴していただき大変ありがたい状況でした。
ただ場所の関係もあり列ができる前に移動される方が多く、列整理システムの稼働は夕方以降になってしまいました。早めの時間に何度か来られてそのまま試聴ができない方もいたように思います。このあたりは今後改善したいと考えています。
当日一部の方に回答した内容の簡単まとめ
- 単体ヘッドフォンアンプについて
ロードマップにも掲載済ですが試聴用試作HPAの話です。今回のイベントのヒアリング結果では試作ハイエンドDACのヘッドフォン駆動力に前向きな意見が多く、興味の中心もそちらに移動したような印象です。そのため現状では単体HPA需要は以前より低下したと予想しています。
また直接は関係のないお話ですが今回の記事の末尾に記載します「高級志向の」単体ヘッドフォンアンプ自体の展開自体可能性が低くなっているように思います。なにかやるとしても現状とは別のプランに変更するべきと考えています。 - 試作ハイエンドDACのライン出力について
背面のXLR出力に入れている抵抗は0.1Ωです。バッファアンプ自体も相当電流を流せる設計です。なので前面のHP端子がなくても背面からヘッドフォンを問題なく駆動できます。このアンプ基板は背面にありますのでレイアウト的に背面出力が合理的です。
これはそれなりのプリアンプに対抗するための設計でありライン駆動力の確保を優先した結果です。その結果ヘッドフォンを駆動できるわけです。もちろん最高峰プリアンプと勝負ができるほどではありませんが定価100万円以内のDACの駆動力としては相当強力なはずで、この価格帯の外部プリアンプなら勝負できる内容だと予想しています。
HP端子オプションは要望が少ないので基本的にヘッドフォンは背面から使っていただくことになりそうです。ただしオプションは要望次第で検討します。 - 試作ハイエンドDACの発売予定について
試作ハイエンドDACの内部の完成度は8割くらいです。ほぼ個別基板で構成されています。これから各部の完成度を上げていく段階ですが、出力バッファ部はほぼ完成、デジタル部は微調整、DAC基板のみ数回の試作が必要という状況です。本体だけなら来年にも量産できると思います。
ただし最大の問題はリモコンです。Wifi接続なのですが時間経過で再接続ができなくなる問題が発生していて調査中です。少し前までは時間経過でハングアップする致命的問題の解決に一ヶ月かかっています。ライブラリの深部のドライバまで調査しているのでかなり時間がかかりそうです。
ハイエンドとしての総合的なラグジュアリー体験を提供するためにはリモコン構想が必須なので、可能な限り時間をかけて完成度と安定性を確保しているのが現状です。ただしあまりにも解決見込みがない場合はリモコンのみあとから発売とする可能性もあります。 - 光ブースター2(仮)について
光ブースタ1とは内容はだいぶ違うのですがまだ名称未定です。これは現状最も発売しやすい製品です。NU-DDCの接続端子拡張(AES、光、同軸の相互変換など)と外部10MクロックとDDC用DC電源のすべての機能を1台で賄う内容です。必ずしもすべての機能を使う必要はなく各機能は個別で動作します。ただし試作ハイエンドDACの開発を優先しているため今のところ開発は優先ではありません。 - Integrated V2について
次に発売見込みが高いのはIntegrated V2です。これはHPA、DAC、Powerの一体型ですがDAC部はJunction DACと同じDAC基板とバッファを載せてさらに発熱余力があればHPA部も強化します。大半は開発済なので工数が少なくアップグレードできる見込みです。
朗報としては発売が遅れた関係でパワーアンプ部もHypex社から最新型が発表されていますのでNcoreX(Nilaiと同じ世代)になります。他のプロジェクトを停止すれば来年には発売でそうですが今のところはハイエンドDACの開発状況次第です。 - Junction DACの再販について
マルチ専用機としてJunction DAC2を予定しています。現在のJunction DAC1と同じものは再販予定がありません。現在のところ2chのDACはハイエンドDACとIntegrated V2が選択肢です。
その他Junction DAC2について重要なご要望があったのですが、5.1chなどのマルチチャンネル対応のリクエストが有りました。これについては何らかの方法でそのような使い方ができるような機能を検討します。せっかくのマルチチャンネル専用機ですのでチャンネルデバイダー以外にも多用途で使える製品を目指したいと思います。
開発優先度は低いのでまだだいぶ先になりそうです。 - パワーアンプ的な製品について
試作ハイエンドDACと対になる製品です。外観は同じでDACとの連携と音質対策の機能が充実する見込みです。従来の純パワーアンプとは設計思想が全く違うのですが詳細はまだ構想段階です。
これは既存のカテゴリではプリメインアンプと呼ばれる内容に近いですが従来の発想の製品とは問題解決の手段が全く異なります。
ただし構想のまま実現するかどうかは試作テストの結果次第なので、さらなる詳細は結果がはっきりした段階で正式に情報公開します。テスト結果を受けて構想自体が変更になる可能性があります。 - 店頭などで聞ける機会を設けてほしい
試作ハイエンドDACの完成度が量産段階になりましたら問い合わせします。現時点では内部仕様が変更になる可能性が高いので中途半端な状態での展示はしません。
ただおいてもらえるかどうかはわかりません。こちらだけで決められる内容ではありませんので交渉の結果不可能になった場合は問題ない範囲でだめな理由と結果を報告します。
ただし試作ハイエンドDACは価格帯的にいままでとは違う顧客層にも届ける必要がありますので、展示交渉は前向きに検討します。また店頭展示によって次にまとめます現状のイベントの問題も解決できます。 - Taiko Switchの影響、Junction DACとハイエンドDACの比較について
当日はTaiko Switchを試作ハイエンドDAC側のシステムのみに使用していましたので2システムに大きな格差があったのですが、18時頃より上流を揃えて純粋にDACのみの比較を展示しました。この音を聞けたのは数人しかいないのですが、結果は思ったほど違いがないとかJunction DACが予想より良いとかTaiko Switchの効果が大きいなど、意見がありました。
これについて詳しく補足したいと思います。
重要なのはDACと上流は相互作用によって出音が決まるということです。Taiko Switchとの組み合わせで全てのDACが良くなるわけではなく、DACのポテンシャル次第です。DAC側の設計の問題が浮き彫りになるだけの可能性があります。
だからこそハイエンドレベルのDAC評価には一線を越えた上流環境が必須ですし、そこでの伸びしろを確保できなければハイエンドレベルとは呼べないわけです。
今回はJunction DACと試作ハイエンドDACはどちらもTaiko Switchによる伸びしろを見せました。またその到達点もそれなりに近いところにあります。これは上流がほどほどであればJunction DACで十分ということです。
そしてまだ無対策の上流+NU-DDCという構成だけでは試作ハイエンドDACの性能を完全に引き出せておらずJunction DACで十分なのが現状です。このあたりも今後研究対象です。
反省点と今後のイベントについての再検討事項
今回午前中はほとんど誰もいませんでした。しかし遅い時間になるほどに人が多く、夕方時点で想定外に待機列が発生し、結果としてJunction DACと試作ハイエンドDACの比較は18時以降の開始でほとんど時間が取れない結果になってしまいました。
聞きたいのに聞けなかった方、すみませんでした。想定外でした。
お客様にとってイベントの目的は複数あると思っています。主に下記の内容です。
- 製品の試聴、比較、検討
- 開発者への質問、要望、確認事項
- 上記以外の交流
現状1年に一度だけではすべての希望に答えられていない実感もあり、現状は時間も場所も足りない可能性があります。とくに試聴は取りこぼしがありそうです。その他はそれなりに対応ができたと思いますが不足があるかもしれません。
純粋な試聴のみであれば本来はヘッドフォンではなくスピーカを鳴らすイベントの機会が望ましいと思いますが、これはなかなか出展のハードルが高く難しいです。当面スピーカイベントはあまり現実的ではないです。逢瀬は販売価格を抑えているので利益の総ボリュームが少なく、相対的に高額な出展費用がきついためです。
そこで今後の解決策ですが一つは店頭への展示、次にヘッドフォンまつりのような小規模イベントの出展を増やすことで状況を改善できると思っています。例えばヘッドフォンまつりminiへの参加を年に追加一回増やし、秋のヘッドフォンまつりとコンセプトを分離するなどです。一つは新製品メインもう一方を既存製品の比較中心とすれば年間で提供できる試聴時間や対応時間は現状の倍です。
これらはまだ決定事項ではありませんが今回の結果を受けて改善できるところは改善していきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
ハイエンド志向のヘッドフォン市場について思うこと
これは今回ではなく以前から少しずつ感じていたことですが、徐々にその流れが強まっていると感じましたので今後の製品展開にも関わる重要なお話ですし一旦ここでまとめて記載しておきます。
ヘッドフォンのクオリティ上昇と価格上昇による階層構造はFocal Utopia SG世代で明確な区切りがついたように感じています。ハイエンド帯は価格はSGと同等以上の製品の選択肢が増えていますが、決定的な差までいかず趣向の深化や先鋭化にとどまっていると予想しています。
これに対して成熟した市場とはもともとそういうもので、ようやくヘッドフォンもそのステージに到達したと喜ばしく感じる方もいるかもしれませんし、ハイエンド志向の市場自体がもともとそのような性格を持っているとも思います。
しかしこのような市場に当社の居場所があるのかは疑問です。
少なくとも逢瀬はこの市場で価格リーダーになるようなメーカーではないと思っていますし、当社のハイエンドラインはすでにハイエンドの入口でしかないと宣言していますし、今以上に先鋭化した単機能のヘッドフォン用機器を作ることは現状の路線からあまりにも離れているとも思います。
それよりは普遍的な基本性能と機能性を充実させつつ現実的な価格に抑えた製品を提供すべきだと考えています。具体的にいえば高額な単体ヘッドフォンパワーアンプのような製品は該当しません。より使い勝手の良いヘッドフォン市場以外でも使える製品です。現状でこれに近いのは次世代ハイエンドDACです(単体プリアンプ並のライン駆動を目指し結果としてヘッドフォンもなるDAC)。
これでも予定価格は100万円弱でまだ高いです。製品ラインナップに象徴として超高額な製品はあっても良いとは思いますが、それしか選択肢がない状況は望ましくありません。ヘッドフォンアンプ目的ならより廉価な選択肢もあることが望ましいです。
そのうえで価格差ほど格差がない十分なリスニング体験を提供したいです。より具体的には今回展示した試作ハイエンドDACの内蔵アンプと比較して、クオリティはできる限り維持して値段は相対的に下がっていくような展開が望ましいです。これは現状のハイエンド市場とやり方が逆ですが進歩とは本来そういうものだと思っています。
とはいえ市場が縮小していくなら安くしても売れるわけではないのでビジネスとして正解ではないかもしれないです。性能向上と低価格の進歩が市場の繁栄を呼び込まない場合、このやり方では投資回収ができなくなるので会社としての先はありません。
ですがそれは高額化でも同じかもしれません。実際のところ最高級ヘッドフォンアンプ製品の長期的な市場実績は、製品の投入は常に断続的というものです。歴史のあるハイエンドブランドの知名度があっても安定してラインナップ継続はできない、これが実績です。具体的な機種名は上げませんが思い当たる製品はいくつか過去にあったと思います。
おそらくですがヘッドフォンアンプは据え置きハイエンドのようにはビジネスとして成立しにくいのだと思います。上記が示すように特殊な高額機の需要はそもそも最初から小さく初動以降は停滞するとしたら、一つのメーカーが取れる販売数では持続不可能です。結局のところ高額化にも先はないようにおもいます。
どちらも先がないならせめて市場の進歩と繁栄の可能性がある前者の選択を取りたいです。幸い逢瀬自体は利益が少なくてもしばらく会社の存続は問題がない状況のため、高額化で生き残りをはかる選択肢は当面は避けます。
以上により単体HPAやヘッドフォンパワーアンプの構想は一旦リセットします。これについてご意見やご要望などありましたらお寄せください。かならずしも対応はできませんが今後の参考にします。